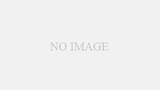「ゲーミングPCが欲しいけど、初心者だとどれくらいの予算が必要かわからない…」「どのくらいのスペックがあれば快適にプレイできるの?」「安すぎるPCを買って後悔したくない」そんな悩みを抱える人は多いでしょう。
ゲーミングPCは一般的なパソコンと比べて高価なイメージがありますが、実は予算や用途に応じて幅広い選択肢があります。この記事では、ゲーミングPC初心者に向けて、予算の目安や価格帯ごとの違い、予算を抑える方法までわかりやすく解説します。はじめての1台を選ぶ前にぜひチェックしてみてください。
ゲーミングPC初心者が知っておきたい予算の基本

プレイしたいゲームによって予算は変わる
ゲーミングPCの価格は、プレイするゲームのスペック要求によって大きく変わります。たとえば「マインクラフト」や「VALORANT」など軽めのゲームなら10万円前後でもOKですが、「Apex Legends」や「Cyberpunk 2077」のような重いゲームを快適に遊ぶには15万円以上の予算が必要です。
ジャンルによっても必要なスペックは異なる
ゲームのジャンルによっても必要なスペックが異なります。シミュレーションゲームやストラテジーゲームはCPUへの負荷が高く、FPSや3Dアクションゲームはグラフィックボードの性能が重要になります。例えば、「Cities: Skylines II」のような街づくりシミュレーションではCPUの処理能力が重視されるため、グラフィックボードよりもCPUに予算を回した構成が理想的です。
画質設定も予算に影響
また、画質設定も予算に影響します。4K解像度や最高設定でプレイしたい場合は20万円以上のハイエンドモデルが必要ですが、フルHD解像度で中〜高設定であれば15万円前後で十分楽しめます。特にeスポーツタイトルは見た目よりもフレームレートを重視する傾向があるため、必ずしも最高画質である必要はありません。
最初に決めるべきは”何に使いたいか”
ゲーミングPCといっても、用途は人によってさまざまです。ゲームだけでなく、動画編集や配信、VRなども視野に入れているなら、それに応じてスペックと予算も上がります。まずは自分が何に使いたいのかを明確にして、それに見合った予算を決めましょう。
配信するならCPUを強化
例えば、ゲームプレイの配信も考えているなら、通常よりCPUの性能を1〜2ランク上げる必要があります。配信中はゲームを動かしながら映像のエンコード処理も同時に行うため、CPUに大きな負荷がかかるからです。Core i5やRyzen 5ではなく、Core i7やRyzen 7以上を選ぶと安定した配信が可能になります。
クリエイティブ作業ならメモリを多めに
また、クリエイティブ作業も行う予定なら、メモリ容量も重要です。動画編集や3DCG制作では16GBでは厳しく、32GB以上が推奨されます。Adobe PremiereやAfter Effectsなどのソフトは多くのメモリを消費するため、これらを使用する予定がある場合は最初から余裕を持ったメモリ容量を確保しておくと安心です。
VR用途はグラフィックボードが重要
VR用途の場合は、グラフィックボードの性能が特に重要になります。VRヘッドセットは両目に別々の映像を高フレームレートで出力する必要があるため、一般的なゲームよりも高い描画性能が求められます。RTX 3070以上、できればRTX 4070Ti相当のグラフィックボードがあると快適なVR体験が可能になります。
10万円以下のゲーミングPCはアリ?ナシ?

軽量ゲームなら10万円以下でもOK
2Dゲームやブラウザベースのゲームなど、スペックをあまり必要としないタイトルを遊ぶなら、10万円以下のモデルでも十分楽しめます。たとえば「原神」や「League of Legends」などは設定を下げれば快適に動作します。遊ぶゲームが限定的なら、ローコストでも満足できる可能性はあります。
入門クラスのグラフィックボードでも十分
この価格帯で見ておきたいのは「GTX 1660 Super」や「RTX 3050」といった入門〜ミドルクラスのグラフィックボードを搭載したモデルです。これらのグラフィックボードであれば、フルHD解像度(1920×1080)で多くの人気ゲームを中程度の設定で動かすことができます。
CPUは新しい世代がおすすめ
CPU選びでは、Intel Core i3-12100FやAMD Ryzen 5 5500といった比較的新しい世代の4〜6コアのプロセッサーを選ぶと、コスパ良くゲームを楽しめるでしょう。
メモリとストレージは最低限確保
メモリは最低でも16GBは確保したいところです。8GBではWindows 11の動作だけでメモリの半分近くを使ってしまうため、ゲームのパフォーマンスに影響が出る可能性があります。ストレージは、OSとよく遊ぶゲーム用に最低500GBのSSDを搭載し、予算に余裕があれば1TB以上がおすすめです。最近のゲームは100GB以上の容量を要求するタイトルも珍しくないため、容量は多めに確保しておくと安心です。
将来性を考えるとスペック不足になる可能性
10万円以下のゲーミングPCは、グラボやCPUの性能がやや控えめです。そのため今は問題なくても、将来のゲームタイトルやアップデートに対応できなくなる恐れがあります。1〜2年先を見据えて選びたいなら、少し余裕のあるスペックを選ぶのが無難です。
技術進化のスピードは速い
ゲーム業界の技術進化は非常に速く、次世代コンソール機(PS5/Xbox Series X)の登場によって、PCゲームの要求スペックも年々上昇しています。例えば2021年に発売された「バトルフィールド2042」は、2018年の「バトルフィールドV」と比較して推奨スペックが大幅に引き上げられました。わずか3年の間にCPUはCore i5からCore i7へ、グラフィックボードはGTX 1060からRTX 3060へと2ランク以上の差が生まれています。
最新ゲームエンジンへの対応
また、Unreal Engine 5などの最新ゲームエンジンを採用したタイトルでは、リアルタイムレイトレーシングやナノポリゴンを活用した超高精細グラフィックなど、従来よりもはるかに高い描画性能を要求するようになっています。現在の予算10万円以下のPCでは、これらの最新技術に対応するのは難しいでしょう。
長期的視点での選択
そのため、長期的な視点で考えるなら、可能な限り最新世代のグラフィックボードとCPUを選ぶことをおすすめします。例えば「RTX 3050」よりも「RTX 4060」、「Core i3-12100F」よりも「Core i5-13400F」といった具合です。わずか数万円の投資で、PCの寿命を1〜2年延ばせる可能性があります。
おすすめ予算帯は15〜20万円。その理由は?

人気ゲームの推奨スペックを満たせる
15〜20万円あれば、人気のFPSやMMOなど多くのタイトルを高画質で快適にプレイできます。例えば「Apex Legends」「PUBG」「FF14」などは、RTX 4060〜4070、メモリ16GB、SSD 1TB程度のスペックで十分対応可能。快適さとコスパのバランスが取れているのがこの予算帯です。
この価格帯であれば、ほとんどの最新ゲームをフルHD解像度で高設定〜最高設定、WQHD解像度(2560×1440)でも中〜高設定でプレイすることができます。特に競技性の高いFPSゲームでは、144Hzや240Hzといった高リフレッシュレートモニターのメリットをフルに活かせるフレームレート(秒間120フレーム以上)を出せるのも大きな魅力です。
カスタマイズの選択肢としては、CPUはCore i5-13600KやRyzen 7 7700X、グラフィックボードはRTX 4060 TiやRTX 4070といった構成が理想的です。これらのパーツは、シングルプレイのRPGや重量級のオープンワールドゲームでも安定したパフォーマンスを発揮します。
また、この予算帯なら冷却性能にも配慮したケースやCPUクーラーを選べるため、長時間のゲームプレイでも熱暴走のリスクが低く、安定した性能を維持できます。特に夏場や室温が高い環境では、優れた冷却システムがあるかどうかで体験品質が大きく変わってきます。
拡張性が高く、長く使える
この価格帯のPCは、マザーボードや電源にも余裕があり、将来的にグラボやメモリを追加・交換しやすい構成が多いです。数年後に性能が足りなくなっても、一部をアップグレードするだけで済むのが大きな魅力です。結果的にコスパも良くなります。
具体的には、15〜20万円のモデルでは700W以上の電源ユニットが搭載されていることが多く、将来より電力消費の大きいグラフィックボードに換装する際も安心です。近年のハイエンドグラフィックボードは消費電力が300〜450Wに達するものもあるため、電源の余裕は重要なポイントになります。
また、この価格帯ではZ790やB650などの上位チップセットを採用したマザーボードが選べるため、CPU冷却や高速メモリのサポート、拡張スロットの数など、あらゆる面で余裕があります。例えば、将来的にM.2 SSDを追加したり、高速なPCIe Gen 4/Gen 5デバイスを増設したりといった拡張が可能です。
メモリスロットも4つ用意されたマザーボードが多いため、最初は16GBを2枚で構成しておき、後から同じメモリをさらに2枚追加して32GBや64GBに増強するといった段階的なアップグレードも計画できます。
初期投資は少し高くなりますが、3〜5年かけて少しずつ部品を更新していける点を考えると、トータルコストでは結果的にお得になることが多いでしょう。また、交換した古いパーツは中古市場で売却することで、新パーツ購入の資金にすることもできます。
予算を抑えるなら中古やBTOも検討しよう

BTOパソコンはコスパ重視の初心者に最適
BTO(Build to Order)パソコンは、パーツを選んで注文できる受注生産方式です。市販の完成品より安く、必要なスペックだけに絞って購入できます。初心者向けモデルを用意しているメーカーも多く、相談しながら選べるのもメリットです。
日本国内にはドスパラ、パソコン工房、マウスコンピューター、フロンティアなど多数のBTOメーカーが存在し、それぞれに特徴があります。一般的に、セール時期を狙うと定価から1〜2万円引きで購入できるケースも多く、同じスペックの既製品と比べてもコストパフォーマンスに優れています。
BTOショップでは、基本モデルをベースにCPUやグラフィックボード、メモリ、ストレージなどを自由にカスタマイズできるため、自分に必要な部分にだけ予算を配分することができます。例えば、オフィス用途もメインで使うならCPUを強化し、純粋なゲーム用途ならグラフィックボードを優先するなど、用途に合わせた最適化が可能です。
また、BTOパソコンの大きな利点は保証やサポートが充実している点です。自作PCの場合、問題が発生すると自分で原因を特定する必要がありますが、BTOパソコンなら1年間〜3年間の保証が付いており、何か不具合が発生した際にも安心です。電話やメールでの技術サポートも受けられるため、PCに詳しくない初心者にとっては大きなメリットになります。
中古PCは注意点を押さえれば狙い目
中古のゲーミングPCは、ハイスペックなモデルを安く手に入れられるチャンスもあります。ただし、保証が短かったりパーツの劣化が進んでいたりする場合があるため、信頼できるショップで購入することが大切です。動作確認済み・クリーニング済みのものを選びましょう。
中古市場では1〜2世代前のハイエンドモデルが新品のミドルレンジモデルと同じ価格帯で購入できることがあります。例えば、新品でRTX 4060を搭載した15万円のPCと、中古でRTX 3080を搭載した同価格帯のPCでは、後者の方が高いゲームパフォーマンスを発揮する可能性が高いです。
中古PCを検討する際は、以下のポイントに注意しましょう:
- 使用年数と使用状況: 販売者が明記している場合は、PCの使用期間やどのような用途で使われていたかを確認しましょう。マイニング(仮想通貨掘削)に使われていたグラフィックボードは避けるのが無難です。
- 保証の有無: 中古専門店では独自の保証(30日〜6ヶ月程度)を付けていることが多いです。トラブル時の対応を考えると、多少高くても保証付きの商品を選ぶことをおすすめします。
- パーツの寿命: 特に電源ユニットは経年劣化する部品であり、3年以上使用されているものは故障リスクが高まります。同様にHDDも機械部品なので劣化しやすく、できればSSDが搭載されているモデルを選びましょう。
- 清掃状態: ケース内部の埃の蓄積は熱問題を引き起こす原因になります。内部清掃済みの商品か、開封写真でケース内部が清潔かどうかを確認できるものを選ぶと安心です。
中古PCはリスクもありますが、適切な知識を持って選べば非常にコストパフォーマンスの高い選択肢になり得ます。特に予算が限られている学生や、試しにゲーミングPCを使ってみたいという初心者にとっては魅力的な選択肢でしょう。
予算に応じたゲーミングPCの選び方まとめ
目的と予算を明確にしてから選ぼう
初心者がゲーミングPCを選ぶ際は、「自分が何をしたいか」と「どのくらい出せるか」を最初に考えることが重要です。やみくもに安いPCを選ぶと後悔する可能性もあるため、予算と目的のバランスを取ることが成功のカギとなります。
予算計画を立てる際は、PCの本体価格だけでなく周辺機器にも配慮しましょう。特に初めてゲーミングPCを購入する場合は、高リフレッシュレートモニター(1〜3万円)、ゲーミングキーボード(5千円〜1万5千円)、ゲーミングマウス(5千円〜1万円)、ヘッドセット(5千円〜2万円)などの周辺機器も必要になります。これらを含めた総予算を考えることが重要です。
また、ゲーミングPCの寿命は使い方にもよりますが、一般的には3〜5年程度と言われています。そのため、「年間でどれくらいの金額を投資できるか」という視点も大切です。例えば20万円のPCを4年使うなら、年間5万円の投資と考えることができます。これを高いと感じるか妥当と感じるかは人それぞれですが、趣味や娯楽への支出として許容できる金額かどうかを冷静に判断しましょう。
最後に、PC購入後のランニングコストも考慮に入れておくと安心です。ゲーミングPCは通常のPCよりも消費電力が高いため、電気代が月に数百円〜千円程度高くなる可能性があります。また、新しいゲームを購入する費用やオンラインサービスの月額料金なども含めた総コストを考えておくと、後から予想外の出費で困ることが少なくなるでしょう。
か分からない場合は、まずプレイしたいゲームの推奨スペックをチェックしましょう。それに合わせてCPU、GPU、メモリの構成を決めれば、失敗するリスクを減らせます。公式サイトやSteamのページに情報が載っているので参考にしましょう。